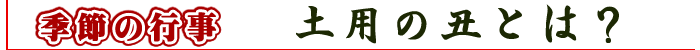【土用の丑とは】
土用とは季節分類の一つである。最近では「土用」というと夏のイメージだが、本来は春夏秋冬、年に4回あり、土用の丑の日は年に何回かあるようだ。
【なぜ土用の丑の日にうなぎを食べるのか?】
万葉の時代よりうなぎを食べる習慣はあったようだが 「土用の丑」にうなぎを食べることをすすめたのは平賀源内という説が有名である。 当時鰻は夏に売れにくく、困った鰻屋が源内に相談したところ「丑の日に”う”のつく食べ物を食べると 夏負けしない」という言い伝えをもとに、「本日丑の日」と店頭に貼るようにとアドバイス。するとその店は 大繁盛し、他の店も真似をしたことから土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が広まったらしい。 他にも”う”のつく食品はいろいろあるが、うなぎは栄養が豊富で夏場に食べるのは理に適っている。
【鰻の調理法】
関東 ⇒ 背開きにして、2~3切れに切り分け竹串を打ち、一度素焼きしてから蒸し、たれをつけて焼き上げる。
関西 ⇒ 頭つきのまま腹開きにし、長いまま金串を打って素焼きにし、たれをつけて焼き上げる。
うなぎのかば焼きは、諸説あるが、串にさして焼いた形が蒲の穂に似ているのでその名が付いたと言われている。
なぜ関東は背開きか。武士の文化が根付いた江戸では腹開き=切腹を意味し、好まれなかったと言う説が有力。
もっとも、蒸すと脂が落ちやすいので、腹の脂が逃げにくい背開きにしたようである。串から落ちずらくもある。
【うなぎの養殖】
現在、うなぎは鹿児島や愛知・宮崎などで養殖されている。
養殖は天然のシラスウナギを捕獲し育てるのである。人工孵化による完全養殖が成功したとの発表はあったが
費用の高さや成功率の低さから商業的にはまだ実用されていない。
天然のうなぎのほうが胴回りが太く、腹が黄色がかっている。
【うなぎの食べ方】
うなぎの食べた方には蒲焼・白焼き・刺身などいろいろある。一番人気は蒲焼であろうが最近では「ひつまぶし」が知られるようになった。 まずうなぎの蒲焼をそのままご飯と共に食べる。次に薬味と共にうなぎを食べる。最後は出汁をかけてお茶漬けにする。 うなぎを3回違った食べ方を楽しめる。
【その他】
昔から有名なお菓子の「うなぎパイ」だが、ちゃんとうなぎエキスが入っているらしい。 他にもパンにはさんだ「うなぎバーガー」もご当地バーガーとして注目されつつあるようだ。
特産品キーワードではウナギを扱っているネットショップを広くご紹介しています。
ウナギ / 浜名湖産ウナギ / 一色産ウナギ / 鹿児島産ウナギ / ウナギの蒲焼き / ウナギの白焼き / ひつまぶし / ウナギの肝 / うなぎの骨
- ※商品情報、店舗情報はデータ取得時のものです。現在の価格ほか、最新の情報は必ず各店舗サイトでお確かめ下さい。
- ※商品の購入は、お客様ご自身と各店舗との間の取引となります。当サイトはここに紹介する店舗との間の取引に一切関与致しません。また、当該取引により発生したトラブル等についても一切関与致しませんので何卒ご了承下さい。
![特産品情報サイト[たくさんとくさん]](/info/eshop/images/takusan_t.gif)